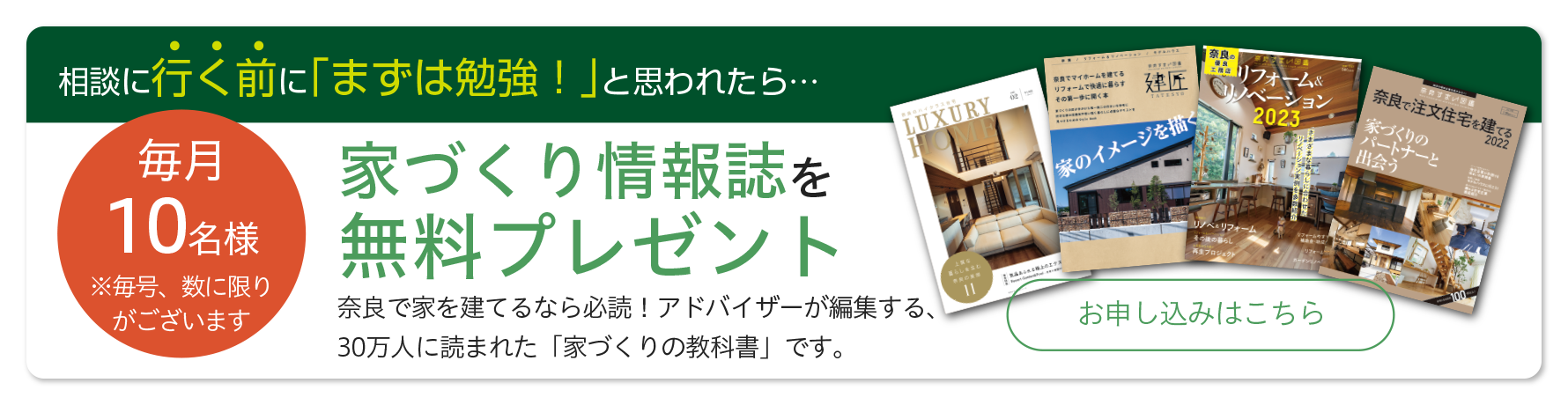マイホームを購入する時、ほとんどの方が住宅ローンを利用します。
「住宅ローン」という融資は、「建物が完成して」引き渡しをされるタイミングで始まります。建売住宅の場合は、もう建物が建っている状態ですので、「契約して居住して住宅ローンが始まる」という分かりやすいイメージがあります。
つまり、「資産として完成した土地や建物=不動産を担保に融資を受ける」、ということですね。
 では多くの方が土地探しから始まる「注文住宅」を建てる場合、それまでに必要な土地購入代金や着工金、中間金などはどう工面すればいいのでしょうか。
では多くの方が土地探しから始まる「注文住宅」を建てる場合、それまでに必要な土地購入代金や着工金、中間金などはどう工面すればいいのでしょうか。
それを解決するのが、「住宅の引き渡し前に必要な資金を一時的に立て替えるためのローン」=「つなぎ融資」です。
つなぎ融資とは?
住宅の引き渡し前に発生する費用の支払いのために利用する融資のことです。
まさに、住宅ローンの契約までを「つないで」くれます。
借り入れた資金は、住宅ローンのように一定額ずつ返済していくのではなく、住宅ローンの融資実行時に、住宅ローンを使ってまとめて返済するのが一般的です。
つなぎ融資を借りるときの返済方法
 つなぎ融資の「元金」は、基本的に「住宅ローン」を実行した時に一括で返済する、という方法が取られます。
つなぎ融資の「元金」は、基本的に「住宅ローン」を実行した時に一括で返済する、という方法が取られます。
しかし、融資につきものの利息部分を、「いつ」返済するかで、総返済額が変わってきます。
返済方法は大きく3つ
①土地購入費から、建物引渡し(住宅ローンスタート)まで、つなぎ融資の元金と利息の支払いはなしにして、住宅ローン実行時に一括返済するというカタチをとる方法
②毎月、つなぎ融資の「利息」だけ支払い、建物引渡し(住宅ローンスタート)後住宅ローン実行時に、つなぎ融資の元金を一括返済するというカタチを取る方法
③つなぎ融資の「利息」だけを「一括」で支払い、建物引渡し(住宅ローンスタート)後住宅ローン実行時に、つなぎ融資の元金を一括返済するというカタチを取る方法
自己資金が少なくても注文住宅を建てられるということは嬉しいポイントですが、つなぎ融資には注意しておきたい特徴もあります。
つなぎ融資の利用前にチェックしておきたい5つの注意点
①住宅ローンと比べて金利は高い
住宅ローンの融資実行時につなぎ融資を一括返済しますが、それまでの期間は利息を支払う必要があり、長ければ長いほど利息の負担が増えてしまうので注意が必要です。
②住宅ローン控除は利用できない
住宅ローン控除には「新築または取得の日から6ヵ月以内に物件に居住し、12月31日まで住み続ける」という利用条件があります。つなぎ融資は引き渡し前の費用に充当されるため、この条件を満たしていません。
③契約に関する諸費用が増える
融資を受けるためには、印紙税や融資手数料、ローン保証料などの諸費用がかかります。住宅ローン1本の場合に比べ、つなぎ融資を受ける場合は契約本数が2本になるため、それぞれに契約費用がかかり、返済負担は大きくなります。
④住宅ローンの選択肢が狭くなる
つなぎ融資は、住宅ローンの融資実行時に一括返済される形をとるので、住宅ローンとセットで同じ金融機関と契約するのが一般的です。そのため住宅ローンの選択肢が、つなぎ融資を用意している金融機関に狭まる可能性があります。
⑤つなぎ融資に住宅ローン控除は適用されない
住宅完成前から借り入れを行うつなぎ融資は住宅ローン控除の適用外ですので、土地取得、着工金・上棟金などは住宅ローン控除を利用できません。しかし建設会社に支払う残金については住宅ローンで精算するため利用可能です。
金融機関別に、つなぎ融資の条件を比較
-
-
- 楽天銀行:同社の住宅ローンに申し込み、住宅金融支援機構の買取仮承認(※以下「承認」と表記。)を取得する。または同社が指定する団体信用生命保険に加入する。
- イオン銀行:同社のフラット35に申し込み、承認を取得する。
- 優良住宅ローン:同社のフラット35に申し込み、融資内定を受ける。または同社提携会社との請負契約に基づき、建設される。
 有名な都市銀行だけでなく、地方銀行やネット銀行も含めて、金利や手数料なども吟味して比較してみましょう。
有名な都市銀行だけでなく、地方銀行やネット銀行も含めて、金利や手数料なども吟味して比較してみましょう。
住宅会社によっては提携している金融機関を紹介してくれる場合もあるので、依頼予定の住宅会社に確認するのもいいかもしれません。
特徴をよく理解してから利用しよう!ご相談は「ナラタテ」へ
つなぎ融資は、自己資金が少なくても注文住宅を購入できる嬉しい仕組みですが、住宅に関わる費用としてはデメリットが多いのも事実です。
つなぎ融資を使わない場合は、同様に住宅の引き渡し前に「土地にのみ」融資を受けられる「土地先行融資(分割融資)」という方法もあります。どちらがよいか、ご利用前によく検討してみましょう。
奈良の住宅会社紹介カウンター『ナラタテ』では、家づくりにまつわるお悩みや疑問にお答えしています。土地購入や注文住宅についての適正予算の算出はもちろん、ローンのご相談やファイナンシャルプランナーのご紹介も無料です。ご予約フォームからぜひお気軽にお問い合わせください。
(最終更新日:2023年1月10日)



 では多くの方が土地探しから始まる「注文住宅」を建てる場合、それまでに必要な土地購入代金や着工金、中間金などはどう工面すればいいのでしょうか。
では多くの方が土地探しから始まる「注文住宅」を建てる場合、それまでに必要な土地購入代金や着工金、中間金などはどう工面すればいいのでしょうか。 つなぎ融資の「元金」は、基本的に「住宅ローン」を実行した時に一括で返済する、という方法が取られます。
つなぎ融資の「元金」は、基本的に「住宅ローン」を実行した時に一括で返済する、という方法が取られます。 有名な都市銀行だけでなく、地方銀行やネット銀行も含めて、金利や手数料なども吟味して比較してみましょう。
有名な都市銀行だけでなく、地方銀行やネット銀行も含めて、金利や手数料なども吟味して比較してみましょう。